『薬屋のひとりごと』第14巻69話「逆子」では、玉葉妃の胎児が逆子である可能性が浮上し、猫猫が触診によってその体位を確認する場面が描かれています。
このシーンは、猫猫の医学的知識と判断力、そして後宮の医療体制の限界を浮き彫りにする重要なエピソードです。
この記事では、猫猫による逆子の触診の具体的な方法や対応、そして物語における意味について詳しく解説します。
この記事を読むとわかること
- 猫猫が逆子を見抜いた触診の具体的手法と観察ポイント
- 後宮の医療体制の課題と帝王切開のリスクについて
- 玉葉妃の決断と猫猫・羅門との信頼関係の描写
猫猫による逆子の触診方法と判断の根拠
『薬屋のひとりごと』第14巻69話では、玉葉妃の胎動に異変を感じた猫猫が、触診によって胎児の位置確認を行う重要な場面が描かれます。
このシーンでは、逆子(骨盤位)である可能性を猫猫が推定し、妃の出産に対する適切な準備を促します。
猫猫の医術的観察力と後宮医療体制の限界が浮き彫りになる、物語の中でも緊張感のあるシーンです。
「下腹部ばかり蹴られる」違和感から始まる推察
物語は玉葉妃の「この子は下ばかり蹴ってくるのよ」という何気ない発言から始まります。
それを聞いた猫猫は、胎児の足が下にある=頭が上にある可能性に気づき、逆子の疑いを持ちます。
この発想は現代の医学に通じるものであり、胎動の位置が胎児の体位に関係していることを示しています。
胎児の体位を見極める触診の手順と観察ポイント
猫猫はまず玉葉妃に触診の許可を得て、慎重に確認を行います。
触診の方法は明言されませんが、妃の尊厳を尊重する形で、婉曲的に「陰部に触れる」とのみ描写されています。
猫猫は胎動の位置だけでなく、胎児の心音の位置や手の感触から総合的に逆子を推定します。
陰部への触診描写と妃の尊厳への配慮
猫猫は、皇妃という立場を持つ玉葉妃に対して敬意を忘れず、触診方法を事前に「こういう方法になりますが……」と囁くように伝えます。
このシーンには、妃の尊厳と医療的必要性のバランスが表現されており、読者に強い印象を残します。
玉葉妃自身も「子どもを産んだときに比べたら大したことないわね」と冷静に応じるあたり、妃としての器の大きさが表れています。
心音の位置と胎動の確認からの推定
猫猫は胎児の心音が腹部の高い位置にあることを確認し、蹴る動きが下に集中していることと合わせて「八割がた逆子」と判断します。
これは現代でも行われる「 Leopold触診法(外診)」に似た技術であり、経験的知識に基づいた判断であることが分かります。
ただし、猫猫自身も「玄人ではない」と語り、判断には限界があることを明言しています。
猫猫の自己評価と技術的な限界
猫猫の医術知識は、直接の教育ではなく養父・羅門の行動を通して学んだものであるとされています。
そのため、自分の判断を「八割がた」と限定的に評価しており、確信を持ちすぎない姿勢が好印象です。
自信過剰ではなく、あくまで経験に基づいた推測として語られているのが、猫猫というキャラクターの誠実さを感じさせます。
逆子判明後の猫猫の対応と医療的リスク
逆子の可能性が高まったことで、猫猫はすぐさま玉葉妃にそのリスクと今後の対処法を説明します。
ここから、出産時の危険性や後宮の医療体制の弱点が明らかになります。
猫猫の冷静な判断力が光る展開となっています。
逆子出産の危険性と猫猫のリスク説明
猫猫は、胎児が逆子のまま生まれる場合、足や臀部から先に出てくることで「産道の損傷や胎児仮死」のリスクが高まると説明します。
これは現代の産科でも共通するリスクであり、物語における医療描写のリアリティを強めています。
同時に、逆子のままでは難産になる可能性が高いため、予防的な対処が必要であると示唆されます。
後宮の医療体制の限界と帝王切開の必要性
当時の後宮には専門的な医師が常駐しておらず、助産婦を一時的に外部から招くしか手段がありませんでした。
猫猫は、最悪の場合は「腹を切る(帝王切開)」しかないと述べています。
しかし、その技術に対応できる人物が現時点で不在であることが、後宮の深刻な問題として浮かび上がります。
養父・羅門の召喚と信頼性への懸念
猫猫は、数少ない信頼できる人物として養父・羅門の名を挙げ、かつて後宮での出産に成功した実績を強調します。
紅娘は羅門が「罪人であること」を理由に強く反対しますが、猫猫は「医官十人よりも優れた腕を持つ」と主張。
玉葉妃の命を守るためには例外も必要であるという、命を最優先にする考えが強く伝わります。
玉葉妃の冷静な判断と壬氏への相談
議論の末、玉葉妃は猫猫の提案を受け入れ、「壬氏に相談して羅門を後宮に呼び戻す」ことを決断します。
この決断は、妃としての強い責任感と冷静な判断力を象徴する場面でもあります。
制度や評判よりも実力を重視する玉葉妃の姿勢が読者の共感を呼びます。
物語における触診シーンの意義とキャラクター描写
猫猫の逆子触診シーンは、単なる医療エピソードにとどまらず、キャラクターの個性や後宮という特殊な社会構造を描く上でも非常に重要な役割を果たしています。
猫猫、玉葉妃、羅門の人物像や関係性が、この場面を通じてより立体的に浮かび上がります。
それと同時に、後宮内の医療制度の不備や、信頼と偏見の間で揺れる人間模様も描かれています。
猫猫の医学知識と後宮内での存在感の強調
触診を通じて、猫猫は医師ではなくとも独自に培った医学的知識と観察力を発揮します。
妃の命に関わる事態に対しても冷静に判断し、実務的な対応ができる存在としての信頼性を高めます。
後宮内の医官よりも優れた実力を持ち、なおかつ謙虚な姿勢で接する猫猫の姿に、知性と人間性の両面での成長が見られます。
羅門の登場が意味する後宮医療の欠陥
猫猫が頼った人物である羅門は、過去に有能な医官として活躍しながらも、政治的な理由で後宮を追放された過去があります。
その存在が再び必要とされる状況は、後宮内における人材不足や制度的限界を象徴しています。
信頼すべき人物が罪人扱いで排除される社会構造の矛盾を、物語は静かに批判しています。
玉葉妃の器量と信頼関係の描写
玉葉妃は猫猫の進言を即座に受け入れ、羅門を呼ぶという決断を下します。
これは単に自身の命を守るためだけでなく、猫猫を深く信頼している証でもあります。
また、紅娘の反対意見に対しても理性的に説得を行い、周囲の意見に流されない強さと柔軟さを併せ持った人物として描かれています。
薬屋のひとりごとに描かれる逆子触診のまとめ
第69話「逆子」で描かれる触診シーンは、単なる医療描写を超えて、物語の核心に関わる重要なエピソードとなっています。
猫猫の成長、後宮の矛盾、そして信頼と人間関係の在り方が凝縮されていると言えるでしょう。
読者にとっても深い余韻を残す、シリーズ屈指の見どころです。
猫猫の活躍と後宮の現実が交錯する緊迫のシーン
逆子という医学的課題に対して、観察力と判断力で切り抜ける猫猫の姿が印象的です。
しかしそれと同時に、後宮の制度の脆弱さが浮き彫りになり、物語にリアリティを与えています。
この対比が読者に考察の余地を与える要素となっています。
歴史的背景を踏まえた医学描写のリアリティ
現代の医療技術が存在しない時代において、触診だけで逆子を推定する描写は、史実にもとづいたリアルな表現といえます。
猫猫の方法は、中世~近代の助産婦が行っていた実践と近く、医学的な裏付けのあるリアルな描写が高く評価できます。
その点で、このシーンは単なるフィクションではなく、歴史医学ドラマとしての深みを感じさせるものとなっています。
読者の関心を集めた婉曲的な表現の妙
触診というセンシティブな行為を、直接的に描かず婉曲に表現することで、妃の尊厳と物語の上品さが守られています。
それでいて、読者には「何が行われたのか」が明確に伝わるバランス感覚が光ります。
物語の緊張感を保ちつつ、品格を損なわない描写は、作画と構成の巧みさを示す好例です。
この記事のまとめ
- 猫猫が玉葉妃の逆子を触診で見抜く場面を詳細解説
- 触診には陰部への配慮が描かれ、妃の尊厳が守られる
- 胎動と心音の位置から八割の確率で逆子と判断
- 逆子出産のリスクや後宮の医療体制の限界が浮き彫りに
- 猫猫が羅門を推薦し、玉葉妃が冷静に決断を下す



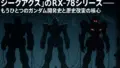
コメント